蛍星

蛍星

闇夜に霞んで浮かぶ朧月を見上げながら男が一人、咥えていた煙管を口から離し、細い紫煙を吐き出した。
開け放した障子窓の柱に背を預け、女物のような派手な柄の着物からは細い足が太腿までむき出しになっている。それでも構わず煙管を吹かす姿は一見無粋に見えるものの、不思議と画になっている。
男は目を細め、月を飽きもせず眺めながらふわりと小さく微笑んだ。
だが直後、一瞬にして緩んだ口許が引き締まる。
目を据わらせて部屋の障子を睨みつけると、人の影が映り込みバンッと足で勢いよく障子が開いた。
「こんばんは。鬼兵隊総督さん」
行儀悪く現れたのはオレンジ色の長い髪の毛を後ろに編み込んだ若い男だった。
男は障子を閉じると断りもなく部屋に上がり込み、にこりと悪びれなく笑む。
「俺が呼んだのは遊女なんだが」
「ああ、知ってる。そこでちょっとおねんねして貰った」
男の言うおねんねが死であることは明確だ。
高杉はあからさまに大きく溜息を漏らすと、少し不機嫌に火鉢にカン、と煙管を打ち付けた。
「騒ぎを起こすんじゃねえ」
「大丈夫だよ。遊郭に死人なんて日常茶飯事なんでしょ」
三つ編みの男、神威は全く笑みを崩さず畳の上に座り込む。
「鬼兵隊の船があるって聞いて俺も降りてきたんだよ。折角会いに来たのに。シンスケに」
「誰が晋助だ」
まだ出会って間もない相手に下の名前で呼ばれ、高杉は眉間に皺を寄せる。
「俺の名前も呼んで欲しくてさ。神威って呼んでよ」
高杉はまるで聞いていないように、煙管に煙草を詰め込み始めた。
「で、何の用だ。春雨の提督さんが」
「だからシンスケに会いに来たの。シンスケは何しに此処へ?」
煙管に火鉢から火をつけて煙を吸い込むと、ゆらりと微笑を漏らす。
「何しにも何も、此処は俺の故郷だぜ」
「ああ、そうだったね。俺の星はとっくに宇宙の塵になっちゃったから故郷なんて言葉忘れてたよ」
「どうせ俺もこの国をぶっ壊すことが目的だ。アンタの星と同じ運命を辿れたら万々歳だな」
「未練はないの? 故郷なんでしょ」
高杉はちらりと神威を一瞥した後、揶揄するように口端を吊り上げる。
それから何も喋らなくなった高杉に肩を竦め、神威は放置されていた酒の盆から勝手に酒を注ぎ喉に流し込んだ。
「故郷と言やあ、そういう歌があったな」
高杉の声に神威が目を上げる。
「へえ。聞かせてよ」
期待感溢れる笑みを刻みながら、神威は銚子を持って高杉の傍に行くと空になっていた杯に酒を注ぎ足した。
高杉は小さく鼻で笑った後、一気に酒を仰ぎ感情ない声で歌い出した。
「うーさーぎーおいしー」
「うさぎって美味しいの?」
ワンフレーズ行かずして神威が突っ込んでくる。
高杉はそういう意味じゃない、と首を横に振りながら「美味しいじゃなく追うってことだ」と説明を入れた。
「続けて」
神威は背を向けると高杉に凭れかかるようにして座り直した。
あまりに無防備な素振りに、高杉は一瞬呆気に取られる。
双方利害が一致した時点で手を結んだ間柄とは言え、敵同士に違いはない。全く警戒していないのは度量か、単に無神経なのか。
そんな高杉も、今は神威の首を取る気分ではなかった。
相手が牙を見せない限り、戦意も何もあったものじゃない。何より…。
「…兎追いしかの山ー」
高杉は気のない歌をまた口ずさみ始める。
20秒程で終わった歌に、神威が顔を擡げ高杉を見上げた。
「…ふうん。意味はさっぱりだけど何だか寂しげな歌だね」
「二番三番もあったように思うが忘れた」
「これはあれかな。ふるさとを思い出して帰りたくなってるワケ?」
「どうだろうなァ」
高杉はくつくつ笑って肩を揺らした。
神威がすぐ傍にあった高杉の白い足に腕を絡ませ擦ってきた。
「…おい」
「女買いに来たんでしょ。俺が変わりになってあげる」
「野郎抱く趣味はねえ」
「じゃあ俺がシンスケ抱いてあげる」
膝立ちになった神威が高杉の顔を覆った包帯ごと愛しむように撫でた。
「正気か」
「そのつもりだけど」
「女みてえな顔したガキがいっぱしに何言ってやがる」
「ひどいな。シンスケじゃなかったら殺しちゃうところだよ」
「そうかい。だったら…」
突然、噛み付くように唇を塞がれた。
互いに目を見開いたまま、熱い唇を合わせて舌を絡ませる。
一方的に神威が舌を使い、高杉は微動だにせず目の前の男を黙って見ていた。
「…つまんないな。俺のキスそんなに下手?」
口を離した神威が少し寂しそうに笑った。
「だから野郎とする趣味はねえって言っただろ」
「嘘嘘。アンタ男の匂いするもん」
けらけら笑った神威が高杉の首筋に鼻をつけて深く吸い込んだ。
「男を知ってる身体だ。獣の、匂いだ…」
ふん、と高杉は薄ら笑い持っていた煙管を傾けた。
まだ煙を噴いている灰が神威の肩に落ち、普通なら声を上げる熱さだが神威はぴくりとも笑顔を歪めなかった。
「夜兎ってのは不感症なのかい?」
「相手によるんじゃないかな。弱い奴とやったって何も感じない」
着物の襟に手を伸ばし、ゆっくりと左右に広げてゆく。
「俺は強い奴にしか興味がない。強い奴は美しいからね」
「……」
露になった胸に、神威の熱い唇が寄せられた。
舌を伸ばしチロチロと肌を味わい始める。
その間も、高杉は黙って胸を這い回る神威の赤い頭を眺めていた。
「…おい」
「ん?」
神威がきょとんとした顔で見上げる。
「するなら布団の上でしろ」
「あはは。そうだね」
神威は無邪気に笑って立ち上がると高杉の手を取り、優雅な足取りで布団の敷かれた隣部屋へと導いた。
「…っ」
後孔に指を入れられた時、初めて高杉が笑んだ口許を引き結んだ。
「慣れてないの?」
神威は嬉しそうに高杉の両膝裏を持ち、高く抱え上げた。
全部見える体勢になり、さすがの高杉も顔を紅潮させて目を背ける。
「照れてる総督さんも可愛いね」
神威は銚子を取ると、高杉の後孔に酒を垂らし指で押し広げ滴らせた。
「悪趣味だなァ、おい」
「アンタ酒が好きだろう? この口からも飲めばいいじゃない」
くく、と高杉は無理な体勢を虐げられたまま笑う。
ぴちゃりと孔に滑った感触が走った。
神威が其処に舌を這わせ、ゆるゆると進入してゆく。
「う…っ」
「ああ、やっぱり。シンスケの杯は絶品だ」
「だから名前で呼ぶんじゃねえ」
「酔っちゃいそう、俺」
神威は指をぺろりと舐めるといきなり指を二本突っ込んできた。
「うあぁ…」
酒か神威の唾液か知らない水音がぐちゅぐちゅと指の動きと共に聞こえてくる。
「あ、あ……」
生理的な涙が一筋高杉の隻眼から零れ落ちた。
全身が燃えるように熱く、中を弄る指が虫のように蠢いて気持ちが悪い。
「んぁ…ッ!」
突然甲高い声が上がった。
神威が一層嬉しそうに笑み、そこばかりを中心に攻め立てる。
「ひゃあぅ…っ! やっ…」
必死で抗おうとする高杉は、侭鳴らない体勢に足をばたつかせた。
「か、神威…ッ!」
ふと指が引き抜かれ、抱えられていた足を下ろされた。
「やっと呼んでくれた」
神威は嬉しそうに微笑むと、ちゅ、と小さなキスを落とした。
「鬼兵隊総督、高杉晋助に告ぐ」
「……」
「入れてもいいかな?」
途端真っ赤になった高杉は、勢いよく足を振り上げた。
「…!」
だが、その蹴りは簡単に片手で受け止められてしまう。
足を持った神威がうっとりと脛を舐めると、びくりと高杉の身体が跳ねた。
「ごめんね。怒らないでよ」
高杉は目を据わらせてじっと神威を見詰める。
「シンスケが可愛くて、エロくて」
「……」
「ガキの俺には堪んないんだ」
両足を大きく広げられたと思ったら、神威の屹立したモノがめり込んできた。
「ぐ、あああっ」
めりめりと音を立て、容赦なく高杉を引き裂いてゆく。
高杉は脂汗を滲ませ、激痛から逃れたい一心で深く息を吐き出した。
「キツイね。チン○食い千切られそう」
「はっ。情緒もないガキらしい感想だな」
痛みからの怒りをぶつけるように毒を吐くと、笑んで細くなった神威の目が僅かに見開いた。
「気持ちよく、してね」
ぐいっと最奥まで抉ると高杉は目を強く瞑り、喉を仰け反らせた。
「はあっ、はあっ……」
神威が動くたびに高杉の足が引き攣る。
口を大きく広げ、端から涎を垂らすほどに顔を大きく歪めているが、その割には漏らす声は小さい。
「声聞かせてよ」
神威は腰を揺らしながら高杉に覆い被さった。
「誰がテメーみたいなクソガキに…」
嬲られてもプライドの高さは変わらないらしい。
神威はぞくぞくと背筋を奮わせた。
この抑揚感は喧嘩と似ている。
「ふふ…。」
嬉しそうに笑いながら、再び神威が腰を使い出した。
「はぁ…ん、あ……っ」
やがて、高杉の口から嬌声のような声が漏れ出した。
いつもより高めに上擦った声は神威の耳を刺激する。
「いいねアンタ、いいよ…」
もはや薬でやられた中毒者のように神威の目には恍惚の光が支配していた。
肌と肌のぶつかる音が絶え間なく続き、高杉も朦朧とした目を薄っすら開く。
揺れる視界の中、普段は穏やかに笑っている男の顔は、いつもとは違った。
いや、違っていたのではない。正確に言えば笑っている。
だが、その笑みはいつも以上に凶悪に優越に、悦楽に歪んでいた。
「あ…あ……」
慣れてきた体は高杉に次なる感覚をもたらしていた。
触れてもいない陰茎は完全に屹立し、先端からは情欲の汁を溢している。
「アンタのそういう顔が見れるなんて、やっぱり会いに来てよかったよ」
神威は嬉しそうに高杉に抱きつくと唇を重ね合わせた。
高杉に抵抗する気力は残っておらず、それよりも吹き上がる淫欲を終わらせるのが先だった。
「もっと…激しく…」
神威の背中に手を回し、耳元に荒れた息ごと訴える。
「ふん」
鼻で笑われたと同時、奥深くに神威の楔が捻り込まれる。
後は息をするのも侭ならないほどに揺さぶられた。
「んあぁ…っ」
絶頂はすぐに訪れ、勢いよく相手の腹を汚す。
だが神威はまるで気付いてもいないように揺する行為を止めなかった。
体位を変え、何度達しても開放されることなく体を貫かれる。
こいつは自分の欲しか追っていない。相手を気持ち良くさせようなんて何も考えていないのだと気付いた。
だが、それが奴らしいと思った。
夜兎という荒ぶる獣の、私欲の塊。
「クク…」
嗤笑を漏らした高杉に、ふと神威が動きを止めた。
「自分だけ気持ち良くなろうなんざ、やっぱりガキだな。提督さんよォ」
一瞬動きを止めた神威が四つん這いになっていた高杉の髪を鷲掴み、上向かせる。
「じゃあ気持ち良くして下さいって言えば」
「誰が言うか」
「ったく…素直じゃないなあ」
高杉は神威の手を掴むと自分の下肢に導いた。
「ほら。一緒にイこうぜ、神威」
途端、ぞわりと神威の背筋が総毛立つ。
やんわりそこを握ると、高杉がひゅっと息を呑んだ。
「…んぁ…は…っ」
摩りながら律動を再開すると、高杉は悦の入った喘ぎ声を漏らし始めた。
内壁が凝縮し、ぎちぎちとキツイ上に絡み付いて離さない。
「なるほど…。確かにこっちのが楽しいね」
ぐいっと高杉の上半身を持ち上げ、自分の膝の上に座らせる。
「あっ、あっ、うく…っ…あん…」
前を同時に扱かれ、高杉は足を大きく割った状態で何度も上下に揺すられた
背後から息を荒げた神威が高杉の首筋に舌を這わせ、時折きつく吸い付いた。
「ん…っ!」
「気持ちいいんだ…?」
「あぁ…、気持ち、い……」
自らもリズムに合わせて腰を揺らめかせる高杉に、神威は目を細めてその姿態に見惚れる。
「ヤバイな…イキそうなんだけど…」
「中には…出すなよ…っ」
なんで?と底意ない顔で神威が問いかけてくる。
「なんでって…おま…っ」
「く…っ!」
高杉が言いかける前に一際深く貫かれ、中にじわりと神威の熱が広がった。
「て、てめ…っ」
「はぁ…っ。シンスケ…」
高杉の声など聞いていないように、神威は恍惚とした表情で全ての欲を吐き出した。
「う…あ……」
抗う力も残っていない高杉は結局神威の大量の精液を受け止める羽目になってしまう。
しかしそれにも感じてしまう愚かな身体は、同時に高杉自身からも何度目かの蜜を吐き出していた。
「ああ…二人でイケたじゃない…」
高杉のモノを後ろから覗き見て、神威は嬉しそうに残り全てを無粋に搾り出す。
「はあ…っ、はあ……」
どさりと高杉が布団の上に突っ伏した。
先ほどまでの圧迫感を失った蕾は白い体液を滴らせながら卑しくひくひくと収縮を繰り返す。
「まだ欲しがってるみたいだけど」
「冗談じゃねえ。これ以上好き勝手されてたまるか」
無理矢理に身を起こすと、高杉は仰向けに寝転がった。
その上にすぐ神威が覆い被さってくる。
「重い。退け」
「兎は寂しいと死んじゃうんだ」
「じゃあ死ね」
「あはは。実はそれガセネタだし」
楽しそうに足をパタパタとさせている神威を、煩わしげに見上げる。
「てめえなんかとやるんじゃなかったぜ」
何故?と神威は笑顔を崩さず訊ねてくる。
しかし高杉は何も答えず、目を腕で覆っているだけだった。
「俺は楽しかったけどな」
ごろごろと高杉に抱きつき、頬を擦り合わせた神威は、ふと、頬の感触に顔を上げた。
「…ねえ。その包帯の下どうなってるの?」
「見てえのか」
「見せてくれるんなら」
「じゃあ嫌だ」
くすりと神威が笑い、少し緩んだ包帯を直してやる。
「でもその包帯似合ってるよ。高杉晋助って感じだ」
「フン…」
「銀髪のお侍さんはその包帯の下、知ってるの?」
高杉は一瞬目を見開いたが、後には遠くを見て口許を歪めた。
「知ってるも何も、奴の目の前で敵に切られたからな。あれからだな、アイツの背中を見るのが嫌いになったのは」
「…?」
「目をやられた俺を庇うようにいつも前に立ち塞がりやがる。鬱陶しいったらありゃしねえ」
言葉ほどに語気に怒りはなかった。
神威は笑顔を引っ込めると身を起こし、裸のままの高杉を見下ろした。
「その銀髪のお侍さんともやったの?」
「ククッ…そんな訳ねーだろ」
「…でもやりたいと思ってる」
神威は高杉に見下ろし、口角を吊り上げた。
いつもは楽しそうに細めている目の奥は異常なほどに輝き、静かな狂気を漂わせていた。
しかし高杉は全く意に介さず、微笑を湛えたままじっと神威の青の目を見つめ返す。
「…ははは。やっぱり侍は面白いね」
「……」
「ねえ、シンスケ。俺はさ、強さしか求めていないんだよ。最強になりたいわけでもない。てっぺんに立ちたいわけでもない」
「……」
「強い奴とやりあってそいつの血を見たい。それだけなんだ。アンタはどう?」
高杉は鼻で笑った後、ゆっくり口を開いた。
「俺はこの腐った世界さえぶっ壊せればそれでいい。それから…」
ん?と神威が首を傾げる。
「俺の欲を埋めてくれる奴がいればいい」
背中に垂れていた長い三つ編みを、高杉が指で引っ掛け弄ぶ。
「…お侍さんは誘うのも上手いらしい」
「勝手に押しかけたのはアンタだろ」
吸い込まれるようにゆっくりと神威の唇が落ちて行った時、
「晋助。時間でござる」
突然ガラリと戸が開いた。
「不粋だね。アンタも侍なら空気読んでくれないかな」
サングラスを掛けた長身の男に向かい、神威が静かな怒りをぶつける。
「まァ、そういうこった」
のそりと神威を押し退け起き上がった高杉は、徐に着物を手にして身に纏い始めた。
神威は口を尖らせるとあからさまに不貞腐れ、布団の上でごろんと寝転がる。
高杉が着替えている間、退屈だと思ったのか襖に背を預けて座ったサングラスの男が徐に背中に背負っていた三味線を構え爪弾き始めた。
透き通るような音色に驚き、神威が男に視線を移す。
「……」
先ほど高杉が唄っていたあの曲だった。
「ふるさと、でござる」
弾き終わると神威に向け、サングラスの奥で男が笑った。
「侍ってのは超能力でも使えるの?」
「まさか。故郷に帰ると口ずさみたくなるだけでござるよ」
「うーさーぎーおいしーだっけ」
男は口端を吊り上げたまま頷くと、高杉の準備が出来たことを確認し立ち上がった。
そのまま出て行こうとした高杉がふと足を止め、布団の上で顎に手を乗せて此方を見ていた神威に振り返る。
「俺はガキの頃、兎鍋が好きだったぜ」
「……」
「なかなか美味かった」
それからパタンと襖は閉じた。
出て行った二人の足音が次第に遠ざかり、完全なる静寂が訪れた。
一人残された神威は、後には苦笑を漏らし大きく背伸びをする。
「そろそろ戻らないとこっちも阿伏兎に怒られちゃうな」
やれやれと言いながら簡単に後始末をして服を着直し寝室を出た。
ふと、火鉢の上に置かれている煙管が目に留まる。
「忘れていったのか」
次会う口実になるな、とクスリと笑い懐に収めようとした時、
「…今度、銀髪のお侍さんに見せ付けてみようかな」
我ながら面白い事を思いついたと、新しい玩具を見つけた子供のように目を輝かせる。
最後に障子窓から淡い光を放つ月を見上げた。
静寂な夜空の下、耳に入るのは遠くから聞こえる虫の声だけ。
「うーさーぎーおいしー……。ああ、やっぱり此処までしか覚えてないや。あとの歌詞はあのお侍さんから習おーっと」
少し重みのある煙管をくるくると回しながら、神威は楽しげに部屋を出て行った。
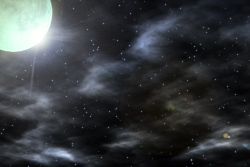
あとがき
突っ込みどころ満載ですみません!!
思ったより難しいカップリングで私、高杉受けの書き方忘れちゃったのかな…と何度も頭を捻りました。
もうね、とにかく神威がよくわかんなくてね。好きなキャラなのにね。うーん…(悲)
いつかまた性懲りもなくリベンジしたいと思います。
ここまで読んで頂き誠にありがとうございました。
戻る