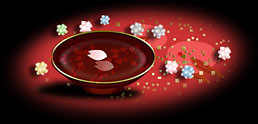
僕たちの季節
「ちっ…雨降ってら」
馴染みの飯屋で昼飯を終えて暖簾をくぐると、外は大粒の雨が降っていた。
濁った空を見上げて土方十四郎は忌々しげに舌打ちする。
勿論傘はもっていない。此処へ来る途中は確かに雲ってはいたが雨は降らないと予想していたのに当てが外れたと深く溜息を吐いた。
仕方がない。もう少し此処で雨宿りして行こうかと元の店に戻ろうと踵を返した時、突然雨から逃れるように駆け込んできた男がいた。
「やれやれ。いきなり降るこたァねえよな」
そう言って憎らしそうに空を見上げた男は、次は土方に向かって苦笑いを浮かべた。
――っ!!
土方は息を詰めて驚いた。
その男の顔に見覚えがある。いや忘れるわけがないのだ。
片目を隠すように巻いた包帯。今にも人を殺しそうな鋭い目と凶悪な表情。
攘夷浪士の中でも最も過激で最も危険な人物として恐れられている鬼兵隊総督、高杉晋助だった。
――なんで指名手配犯がこんなところに?!
思わず叫び出しそうになった土方に、高杉がにこやかに笑って「アンタも雨宿りかい」と人の良さそうな笑みを浮かべた。
――…あれ? ひょっとして俺の事気付いていないのか?
土方は一瞬声を飲み込み、目を大きく見開いた。
それはそうだろう。今日は仕事がオフだ。いつもの隊服ではなくプライベート用の着流しを着ている。
真選組副長とは言えそんなに顔が割れているわけではないだろうし、情報が正しければ今の高杉の拠点は京のはずだ。江戸に住んでない輩なら特に顔など知らないだろう。
「飯、食わねえのか?」
高杉の声にはっとして、土方は慌てて平静を装い「食ったばかりだ」と硬い口調で笑い返す。
「俺も食ったばかりで腹減ってねえんだよな。それより酒でも飲みたい気分だ」
――この野郎…。変装もせずのうのうと俺の前に姿を見せやがって。この場で粛清してやろうか…。
土方の胸にメラメラと敵愾心の炎が滾り、笑みが浮かび上がる。
「どうした、お兄さん? 俺の顔に何かついてるか?」
またもや土方ははっとして息を呑んだ。
「あ、ああ。いや…はは…そ、そうだな。参ったな、この雨」
高杉の話など上の空の土方は必死に話を取り繕おうとした。
――そうだ。今こいつを粛清するのは簡単だが、こいつの後ろには数え切れないほどの隊士がついている。まず鬼兵隊中枢の動向を探り、それから一気に畳み掛ける! これだ! へっ…高杉め。俺に声をかけたのが仇となったな。今日がお前の本当の意味での命日だ!
「こんな真昼間じゃ酒出してる店なんて宿くらいしかねえだろう。どうだい、お兄さんも付き合わねえかい?」
「あ、ああ。いいな」
すぐそこにあったぜ、と言う高杉に連れられ雨中の路上を飛び出すと、その店を目指し走った。
3分ほど走ったところで、店の中へと滑り込む。
店には番台に一人の中年女性が座っていて、ずぶ濡れの土方たちにも嬉しそうに接客し部屋へと案内してくれた。
「すぐお酒用意しますからね。これで体を拭いてお待ち下さい」
気の良い女将の気の回しように、助かるよと土方も快く手拭を受け取る。そしてぱたん、と襖が閉まったと同時、土方ははっとして顔を上げた。
――し、しまった! もしかしてこれって奴の懐に飛び込んできちまったんじゃ…!
どくんどくんと心臓が早打ち始める。
――ありえる! 人の良さそうなふりして俺を誘い込み二人きりになったところで一気に斬りかかる。もしくはこの後部下の浪士たちが一斉に乗り込んできて俺を囲み…!
「おい」
びくっと肩を大きく揺らし、土方は青い顔で振り返った。
「手拭、俺にも貸してくれや」
一瞬拍子抜けしたが、まだ奴の企みが勃発していないだけなのかも知れない。
土方は手拭を渡しながらも高杉の一挙一動に目を血走らせた。
しかし高杉は妙な動きを見せることなく濡れた体を大雑把に拭うだけで、腰の刀も邪魔だとばかりにそこ等に放り投げる。
「……」
「アンタも座れば?」
言われて土方もゆっくりと畳に腰を落とす。
しかし刀は邪魔でも抜かなかった。いつ奴が隙を狙ってくるか分からないのだ。
そのすぐ後に女将が酒と肴の乗った盆を持って置いていく。
「どうした、口数少ねえな」
――そうだ。今はとにかくこいつの動向を聞き出すのが先決だ。これが奴の挑発ならこっちも乗ってやろうじゃないか。
「ち、ちょっと人見知りでね。初対面のお侍さんと二人だけで飲むのは初めてだから」
「そうか。まあ酒が入れば少しは気も抜けるだろうよ。ほら飲め」
そう言って高杉が銚子を取って酒を注いで来た。
土方も不審な動きを悟られまいと必死に取り繕って受けた酒を飲み干す。
いい飲みっぷりだと笑った高杉も、同じように杯を傾けた。
「お、お侍さんはこの辺の者じゃないだろ。どこから来たんだい?」
出来るだけ平静を装い、土方は早速質問という名の尋問に入る。
「お侍さんはやめてくれよ。俺ァ高杉ってんだ。京から来た」
――やはり高杉だ! しかも堂々と名乗りやがった。やはり俺の事は知らないんだな。
確信を持った土方はにやりと胸中でほくそ笑み、そうかいと笑って返す。
「そりゃ遠い所からようこそ。江戸まで何しに来たんだい?」
核心を突く物言いは胡散臭く思われるだろうか。
「連れがな、芸能界の仕事に携わっててプロデューサーだからどうしても現地で打ち合わせしなければいけないからって」
「……は?」
一瞬何の事かと目を丸くする。
――そ、そうか嘘か! ふん。さすが凶悪犯罪者。芝居はお手のものだな。
騙されるものか、と土方は気のない相槌を打った。
「アンタは?」
「へ?」
「アンタの名前だよ」
言われてぎくりと肩を揺らす。
土方なんてあまりない苗字だ。もしかすると真選組隊士の名前くらいは覚えられているかもしれないし、気付かれるかも知れない。
近藤、沖田然りだ。山崎…いやいやこんな地味な隊士でも知らないとは限らない。
「さ、坂田だ」
咄嗟に名乗った名前はいつも対峙している万屋屋の銀髪頭の男だった。
奴の名前を仮とは言え名乗るのは心許ないが、坂田という苗字くらいなら何処にでもありそうだし気付かれることもないだろう。
「坂田か。そういや俺の昔の知り合いにもいたな」
「えっ」
土方は驚いて箸を落としそうになった。
――ま、まさかあの天パー野郎、高杉と知り合いなのか? 桂ともどうも繋がりがあるような節もあるし…。
土方の中で今関係の無いはずの男の顔が浮かび上がり怒りが込み上げてくる。
「ガキの頃、同じ寺子屋に通ってたんだ。いつも薄汚れた汚い着物着て周りの連中を一歩離れたところから冷めた目で見てるような奴だった」
「……」
「でも何故か人気あったんだよな。喧嘩が強くていざと言う時はみんなが頼りにしてた。そのせいか先生からも一目置かれていた所は嫌いだったがな」
懐かしむように笑う高杉に、何故か土方は敵対心を忘れて聞き入っていた。
「悪いな。俺の話ばかりしてもつまらねえだろう」
「いや…もっと聞かせてくれよ」
高杉晋助という男が知りたい。
高杉の言う坂田があの万事屋とは違うかも知れないが、それでもこの男がどういう過去を持っていて、どういう人間に感銘を受けてどういう経緯でこうなったのかを知りたかった。
「坂田…下の名前はなんて言うんだ?」
「え…十四郎」
一瞬はっとして口を押さえかかった。
――バ、バカか俺は! 折角苗字は偽名使ったのに下の名前だけ本名名乗ってどうするんだ!
焦る土方に気付いてもいないように、高杉は「十四郎か」と笑いかける。
「……」
どうも調子が狂う。
それもこれも自分のイメージしていた高杉と違いすぎるからだ。
今まで何人もの幕府役人を殺してきた殺戮者とは思えない。
今目の前にいる屈託の無い笑顔を浮かべて自分と向き合っている男は、本当にあの高杉なのだろうか。
「雨、やまないな」
ふと、高杉が襖の奥で激しく叩きつける雨音に耳をすまし呟いた。
「あ、ああ。梅雨だからな。仕方ねえ」
油断してなるものかと土方は腰の刀を確認するように隠れて撫でた。
「梅雨か…梅雨が終われば夏が来るな。夏は好きかい?」
「まあ嫌いじゃねえが、夜寝苦しくなる時は嫌だな」
「俺は好きだ。開放的になって楽しくなる。祭りも多いしな」
祭りと言われて土方の眉根がぴくりと上がる。派手な祭りや破壊を好む、やはりテロリストか。
再び湧き上がりだした疑念を思い出し、少し自分を落ち着けようと着物の袂から煙草を取り出し火をつけた。
「まあ俺が夏生まれってのもあるかも知れねえな。アンタは何月生まれだい?」
言われた質問に「五月だ」と土方は素っ気無い身振りで煙を吐き出した。
「季節は春かも知れないが、暖かいのか寒いのか分からない月だな。だからあまり好きじゃない」
「それも一興じゃねえか。今年の誕生日は暖かいのか寒いのか考えるのも楽しいだろう?」
土方は少し面食らい、咥えた煙草を落としかけた。
そんな事考えたこともなかった。毎日が忙しく自分の誕生日どころか季節の移り変わりさえ気付かず、気に留める余裕もなくなっていたのだ。
しかしこいつは目を細めて障子の向こうを慈しむように見つめている。
まるで雨も風情があると言うように。
少し羨ましいと思った。
すると、高杉が自分の着物の袂から何か取り出した。
一瞬びくりとした土方だが、それが煙管だと気付くと詰まりかけた息を隠れるように吐く。なんだかいちいち反応してる自分が滑稽だ。
高杉は煙管に慣れたように葉を詰め込むと、マッチで火をつけた。
「…煙管…か」
思わず呟くと、高杉が目を細めて旨そうに煙を吐き出した。
「アンタは煙草派みたいだな。俺も試したことあるがどうもしっくり行かなくてな」
「煙管は試したことねえな。持ち運びが不便そうだと思って」
実は隊服に合わせてこれにしたとは言えない。洋装では煙管はポケットに入りきらないのだ。
土方が苦笑いを浮かべ煙草を翳すと、「違いねえ」と高杉も同調し肩を震わせ笑った。
「でも煙管も悪くねえぜ。どうだ、試してみるか?」
「い、いや。いい」
慌てて首を振ると、土方は誤魔化すように酒を注いで一気に飲み下した。
――俺は何をやっているんだ。敵と世間話みたいな事をして…。本来の目的を忘れるな…!
自分を叱咤するように心中で力強く叫ぶ。
「どうした? 黙り込んじまって」
「あ…い、いや」
「酒には弱いのか? 顔が赤いが」
はっとして顔を上げる。
土方は酒は嫌いじゃないがあまり強くはない。すぐに酔って顔に出てしまう体質なのだ。
一方の高杉は同じ量、もしくはもっと飲んでいる風なのにまるで顔に出ていない。かなり酒豪のようだ。
「はは…弱いつもりはないが、こんな昼間っから飲むのは気が引けらぁな」
いい訳しながらも思ったより呂律が回らなくなっている。体は酔っても精神は折れるまいと、土方は必死で目を剥いた。
「ここまで来てそりゃねえだろうよ。一度つけた酒は最後まで美味しく頂こうぜ」
そう言って高杉は自分の盆の銚子を持つと徐に立ち上がり、土方の側まで寄ってきて隣に座り込んだ。
「な、何…っ」
「此処で会ったのも何かの縁だろ」
「……」
この男は本当に疑っていないのだろうか。
指名手配犯がまるで警戒心なく初対面の人間をこんなに信用して…馬鹿にされているような気もする。
杯に並々と注がれた酒。男義まで試されているようで、少々憤慨した土方は思い切って一気に飲み下した。
高杉は上機嫌でそれを見て微笑し、自分も習うように豪快に喉に流し込む。
――油断するな。奴の刀は部屋の隅だ。他に武器を仕込んでいるような素行はないし、戦いなら絶対に俺が有利…――。
しかし土方の頭は酒のせいでどんどん思考力を奪っていく。視界は二重に見えてくるし、体中が火照っていて熱い。眠気まで襲ってきた。
――だめだ。ここで倒れたら斬られる。こんな所で死んだら近藤さんに申し訳が立たねえ…真選組も…。
頭でぐるぐると理性と感情が行き来しているうちに体がぐらりと傾いた。
――くそ…起きろ十四郎…高杉が…。
「…?」
とろんとした目を開けると、目の前に何かが覆い被さっていた。
そして唇に感じる生暖かい感触。体に圧し掛かる重み。
「ん…んん?!」
大きく目を開けた先に、にやりと微笑む高杉の顔があった。
「無防備だなぁ…アンタ。可愛いね」
「……!!」
土方は途端酔いが吹っ飛び、慌てて起き上がろうとした。
だがすぐに肩を捕まれ再び畳の上に押し倒される。
「な、なな…!」
驚きすぎて声が出ない。今何をしたこいつ? キ、キ、キ…!
「そのまま酔ってろよ。何も考えるな」
「ふ、ふざけんなっ! 俺は男だぞ!」
当たり前の事を叫んでも奴はクククと肩を震わせ笑うだけだった。
「いいじゃねえか。初めて会った者同士が酒の席で過ちを犯したってのは男と女でもよくある事だろう?」
「だから俺は男だって…!」
「俺は抵抗される方が燃えるタチでねえ…」
「は?」
「女は従順で好かねえ。これくらいが面白い」
「何言って…!」
反抗の言葉は再び唇で塞がれた。
「ん…!」
口腔で舌が乱暴に這いずり回っている。押し退けようとするも、高杉の舌は逆にそれを捕えて執拗に絡み付いてきた。
「んん…っ、ふ」
だんだん息が上がってきた。いつの間にか肌蹴られた着物の下を無遠慮に高杉の手が撫で回している。
「や、やめ…っ」
必死で体を捻り逃げようとするが、酒の影響かまるで力が入らなかった。
「あ…!」
突然下肢を下着の上から握り込まれる。
「なんだよ。しっかり反応してるじゃねえか」
嬉しそうに高杉は下着を脱がし始め、そして直ぐにまた握り直した。
「く…っ、ん……」
人に触られるのは慣れていない。
そこは想像以上の反応を見せすぐにダラダラと先走りを溢れさせる。
「やめ…たか、すぎ…っ」
「もっと名前呼べよ。ゾクゾクする」
耳元に舌を這わせる高杉の息も乱れている。
「くそ…こんな……っ」
こんなはずではなかった。自分は職務を遂行しようとしていただけなのに。
「ひ、ああっ!」
どくん、と勢いよく欲が弾けた。
「早いな。ドロドロじゃねえか」
高杉が見せ付けるように今しがた自分が吐き出した体液を指から滴らせる。
「な、何なんだてめえ…」
土方の声など聞いていないように、高杉はまた覆い被さり胸を舌で舐め上げた。
「も…よせ…」
「これからだろ? 俺にもそういう顔させてくれよ」
「…?」
「気持ちいいって顔」
「…っ!」
ずぶりと想像もしなかった箇所に指を入れられた。
「ん…や、やだ…っ!」
後孔で暴れまくる指が気持ち悪い。吐きそうだ。土方は本気で嫌がって涙を滲ませる。
「あ…っ!」
突然、思いもよらない声が上がった。
驚いたのは土方だ。自分の口からこんな声が出るなんて恥ずかしすぎて動揺する。
「ほう。ここか」
高杉は面白いものを見つけたとばかりに今度は其処ばかり攻め立てた。
「ひ…っ、あ…んぁ…!」
初めての感覚に土方はどうしていいか分からず身悶える。
声が止まらず体が引き攣るように震えている。
「いい声で鳴くじゃねえか。想像以上だ」
遠く聞こえる高杉の声に、土方は必死で首を振った。
するといきなり指を抜かれる。
そして足を持ち上げられたかと思うとその隙間に高杉の膝が入ってきた。
「な、何…」
まさか、と一気に顔が青褪める。
「力抜け」
「え…うぁ…っ!」
指以上の太さのモノが強引に押し込められる。
「い、痛…あ……!」
「息吐けよ。裂けるぞ」
裂けると言われて背筋が凍りつく。気付けば言われた通り震えながら息を吐き出していた。
「そうだ。いい子だ…」
痛みより圧迫感の方が苦しかった。
容赦なく腸まで届きそうな異物は一体何処まで侵入しようとするのか。
「ふ…全部入ったぜ…」
少し息を弾ませた高杉が土方の目尻に指をかけてきた。
どうやら少し泣いていたようだ。ぐいと涙を拭われる。
「そんな慌てるんなよ。今動いてやるから」
震えて凝縮をしている後孔を勘違いしているのか、微笑を浮かべた高杉がそう呟いた。
「ふざけんな…っ」
「ここまで来てまだ悪態吐くか。いいなァ…お前。やっぱりそそる」
「くぅ…っ!」
突然大きく突き貫かれた。
土方が悲鳴を上げる間もなく、激しく何度も叩きつけられる。
「あ、あ、あぁ…!」
漸く声が出てきた頃には、もう快楽だけを追っているように抵抗なく揺さぶられているだけだった。
「はっ、はっ…んん…!」
「善くなってきたか? ここもダラダラ零してやがるぜ」
前を擦られまた高い声が漏れる。
こんなのは知らない。一点の場所を突かれる度に何とも言えない至上の快楽が土方の思考もプライドも全てを奪っていく。
目から新たな涙が零れ落ち、開け放したままの口からは透明の露が畳に染みを作った。
「あ、あん…っ、高、杉…っ…高杉ィ…っ」
激しすぎる律動におかしくなりそうで、土方はやめて欲しくて必死で名を呼んだ。
「ああ…もうイく…」
荒い息で高杉が耳元で囁いた。
違う、と言いたいのに声は言葉にならず喘ぎ声だけにしかならない。
「くぅ…っ…あ、あ……!」
「十四郎…」
唇を塞がれる。気付けば土方も舌を出し唾液を垂らしながら高杉の唇を貪っていた。
「ん…ふ…ああああ――っ!」
ビクンと全身が脈打った。
どくどくと白濁が高杉の手の平を濡らす。
「十四郎…っ」
その後、体の深くに何かが弾けた。
じわりじわりと自分を侵食して行くような妙な感覚。
最後、自分を呼んだ名前に不思議と心地よさを覚える。
その後は襲い来る睡魔に負け、そのまま重い目蓋を閉じた。
「……ん」
遠くで何か話しているような声に、ふと目を覚ます。
「ああ、分かった。あと三十分で行く」
「……」
朦朧とする意識で見上げると、携帯電話をパタンと閉じた高杉と目が合った。
「よォ、起きたかい」
飄々とした顔で笑みを浮かべる高杉を憎らしげに睨みつける。
「俺…どれくらい寝てた?」
「二十分くらいだなァ。体辛いだろ? もう少し寝てたらいい」
「無茶苦茶しやがって…」
「そうか? 俺の割りには優しかったと思うがなァ」
抜かせと言いながら体を起そうとして、下肢の激痛に瞬時に顔が引き攣った。
「クク…」
それを見て楽しそうに高杉は笑い、煙管を取り出し火をつける。
この男の言うことなどには同意したくないが、腰の鈍痛には耐えられず土方はまた再び畳に突っ伏すしかなかった。
目だけそっと高杉を見上げれば、煙管を咥え紫煙をたゆたせている。
その様が何だか絵になるなと見惚れてしまう。
片目は包帯で覆われているため表情はよく分からないが、精悍な横顔と乱れた派手な柄の着物が色香を漂わせている。
色気のある男ってのはこういうものかと土方は感慨深く見つめていた。
「どうした?」
「あ、ああ。いや」
少し赤くなってそっぽを向く。
そう言えばコイツは敵だったと今更気付いたように頭を数回振った。
「これ、やってみるか?」
「え?」
突然口元に煙管を咥えさせられた。
ほら、と高杉が楽しそうに笑っている。
「……」
土方は高杉を上目遣いで睨みつけたまま、何も言わず煙を吸い込んだ。
「ご…ごほっ!!」
思いも寄らぬ喉への刺激に思わずむせ返る。
「ひゃはは。ちょっと強かったか」
高杉は人事だと思って爆笑している。それを恨めしげに睨むも、堰は止まらない。
「それ、やるよ」
「は?」
漸く止まった堰を宥めていたら、思わぬことを言われて驚いて振り返る。
「次会う時は上手く吸えるようになっとけよ、真選組副長の土方さん」
「――っ!!」
驚いて目を丸める土方に構うことなく、高杉は颯爽と立ち上がり、乱れた着物を簡単に直すと部屋の片隅に置いてあった刀を取り上げた。
一瞬ぎくりとした土方だったが、高杉はまるで闘争心の欠片も見せずに普通に腰帯に刀を差し、襖に手をかける。
「あ……」
何か言おうとして口を大きく開けかけると、高杉が微笑を浮かべて振り返った。
「雨は闘争心が削がれていけねえや。かえって温もりを求めたくなる」
「……」
「次に会う時はその煙管上手く吸えるようになっとけよ。十四郎」
「次会った時は斬る」
突然降ってきた土方の鋭い声に、高杉は一瞬目を見開いた後、またくつくつと笑って目を細めた。
「ああ、思い出ごと斬っちまえばいい。次会うのが楽しみだなァ」
それを最後に高杉は襖を閉め、出て行った。
暫く微動だにせずその襖を睨みつけていた土方だったが、次には深い息を吐き出し肩を落とした。
そしてゆっくりと手に持っていた煙管を持ち上げる。
まだ細く煙が上がっている葉を見届け、恐る恐る口元に近づけると慎重にそれを吸い込んだ。
「…ま、悪くねえな」
少し冷えて肺に入ってくる煙は、不思議と優しい安堵感に包まれた。
土方が店を出た時には、雨はすっかり上がっていて雲の隙間から夕暮れの日差しが射していた。
「あれ、土方君じゃん」
覚えのある声に振り返ると、銀髪頭の男が相変わらず緊張感のないヘラヘラした笑みを浮かべながら此方に向かって歩いてきた。
「丁度良かった。甘い物でも食いにいかねえ? てゆーか奢ってよ」
「……」
いつもの反応もなく黙ったままの土方に、銀時があれ?と拍子抜けして目を丸くする。
「どったの?」
「お前、高杉って知ってるか?」
突然の質問に一瞬銀時の目が窄められたが、すぐ後には「知らねーよ。誰だそれ」とつっけんどんに返された。
「そうか…だよな…」
少し残念そうに鼻で笑う土方が、銀時にはちょっと寂しそうに見えて困惑する。
「そう言えばガキの頃に似たような名前の同級生がいたような…」
土方は相手にしてないように「またジャンプ貸しっぱなしにしてたって話かよ」と言い捨て歩き始めた。
その横を並ぶように歩きながら、銀時が「違う違う」と苦笑いを浮かべた。
「ぼんぼんのくせに何をトチ狂ったのか俺たち貧乏寺子屋に通ってる変なガキだった。先生の前ではいい子ぶってるくせに、ガキ同士になると途端に目ェ吊り上げて食って掛かる可愛くねえガキだったよ」
「……」
「チビとかぼんぼんだからってバカにされるとすぐ飛び掛ってきやがる。血の気が多くて負けず嫌いで。でも自分の信念を絶対に曲げない所は見ていて面白かったな」
「……」
不思議とこの男と高杉の幼少時代が重なって見えた。
どちらも一致した確証はないのに、何故か二人はとうに出会っていたような感覚をもたらす。
「今頃何やってるんだろうねえ。今でもチビなのかな」
ぎゃははと笑う銀時を横目に、土方もふっと笑って袂の中の煙管を握り締める。
「万事屋、甘味屋行くか」
「あ? こりゃまたどういう風の吹き回し?」
「晴れたから気分いいんだよ。煙管も吸いてえし」
「キセル? お前タバコ派じゃなかったっけ」
「着物の時は煙管になったんだよ。粋だろ?」
「この中二病がっ」
ぎゃんぎゃん喚きながら水溜りの道を掻き分け歩き出す。
その頭上の空を、一隻の大きな船が轟音を立てて飛び立っていった。【終】
――これがこれであるように
それはそれであればいいと思うよ
たぶん――【僕たちの季節】

あとがき
ここまで読んで頂きありがとうございました。
初の高杉攻め。難しかったけど楽しかったです。
土方はおちょくってなんぼだと思うので思う存分書けて良かった。しかしその分高杉がよく笑うなぁ。キャラおかしいよ(笑)
タイトルは勿論DOESさんのあれですよ(笑)
私はバクチダンサーよりこっちのが好きだな、と友達に言ったら「タルいからやだ」と返されました。
いいじゃん!タルくてもいいじゃん!ねえ?!(誰に言ってる)